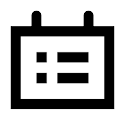皆さんは「埋伏歯(まいふくし)」という言葉を聞いたことがありますか? 代表的なものとして、親知らずと聞くことが多いかもしれません。歯茎の中に完全に埋まっていたり、一部だけ顔を出していたりして、正常に生えきることができない状態の歯のことです。特に親知らずでよく見られますが、他の部分の歯や過剰歯でも起こることがあります。埋伏歯は高頻度でみられる歯の位置異常のひとつで咬合状態にさまざまな影響を及ぼします。
今回は、矯正歯科でよく扱う「埋伏歯」について、その原因や治療法、注意点をわかりやすくご紹介します。
◆ 埋伏歯とは?
埋伏歯とは、あごの骨や歯ぐきの中に埋まったまま、正しく生えてこない歯のことを指します。
特に多いのは「親知らず」ですが、次いで上顎犬歯、下顎第2小臼歯、上顎中切歯で、永久歯が生えてくるべき時期に出てこないケースもあります。

◆埋伏歯の原因
- スペース不足: 顎のサイズと歯のサイズに不調和がある場合、すべての歯が収まるスペースが足りなくなることがあります。
- 歯の生える方向の異常: 歯が正しい方向に向かって生えてこないために、隣の歯にぶつかったり、骨に引っかかったりして埋伏してしまうことがあります。
- 乳歯の早期脱落や残存: 乳歯が早く抜けすぎたり、逆に永久歯が生える時期になっても乳歯が残っていたりすると、永久歯の生えるスペースが失われたり、生える方向がずれたりすることがあります。
- 遺伝的な要因
- 歯の数が多い(過剰歯がある)
- その他: 歯の形の異常や、嚢胞(のうほう)などの病気が原因で埋伏することもあります。
◆ 矯正歯科でのアプローチ
矯正歯科では、レントゲンやCTを使って歯の位置を正確に把握し、必要に応じて以下のような治療を行います。
1. 埋伏歯の牽引(けんいん)
歯ぐきを開いて埋まっている歯に小さな装置をつけ、矯正装置でゆっくり引っぱりながら正しい位置に導く治療です。


2. 抜歯
向きが悪く他の歯に悪影響を与える可能性がある場合、抜歯を選択することもあります。
3. 歯列のスペース確保
埋伏歯が出てくるためのスペースを矯正治療でつくることもあります。
◆ 治療を始めるタイミング
小児期からの経過観察がとても重要です。
レントゲンで歯の数や位置を早めに確認し、必要に応じてⅠ期治療(小児矯正)を行うことで、埋伏歯のリスクを減らせる場合もあります。
◆ 放置するとどうなる?

- 周囲の歯への悪影響: 埋伏歯が隣の歯を押し続けると、隣の歯の根を吸収して歯が脆くなったりすることがあります。
- 他の歯を押して歯並びが乱れる
- 炎症や感染: 埋伏歯の一部が歯茎から顔を出している場合、その隙間に食べかすやプラークが溜まりやすく、細菌が繁殖して**炎症(歯周炎)**を起こすことがあります。ひどくなると、顔が腫れたり、発熱したりすることもあります。
- 虫歯: 歯ブラシが届きにくい位置にあるため、埋伏歯自体やその隣の歯が虫歯になりやすくなります。(第3大臼歯の場合の半萌出)
- 嚢胞(のうほう)の形成: 埋伏歯の周囲に液体がたまり、嚢胞という袋状のものができることがあります。嚢胞が大きくなると顎の骨を破壊したり、周囲の歯を圧迫したりする可能性があります。
- 痛み: 炎症や嚢胞が大きくなると、強い痛みを感じるようになります。
【Q&A】埋伏歯
Q1. 埋伏歯(まいふくし)って何ですか?
A. 本来生えてくるはずの歯が、あごの骨や歯ぐきの中に埋まったまま出てこない状態のことです。
特に多いのが「親知らず」や「上顎の犬歯」です。前歯が埋伏するケースもあります。
Q2. どうして埋伏してしまうのですか?
A. 歯の生えるスペースが足りない、歯の向きが悪い、乳歯が長く残っている、過剰歯があるなどが原因です。
遺伝的な要因もあり、家族で似た傾向が見られることもあります。
Q3. 埋伏歯は矯正治療で治せますか?
A. はい、多くの場合は矯正治療で引っぱり出す(牽引)ことが可能です。
歯ぐきを少し開き、歯に小さな金具をつけて矯正装置でゆっくりと正しい位置に導きます。
Q4. 治療はいつ始めればいいですか?
A. 小学校中〜高学年の頃にレントゲン検査で発見されることが多く、早めの相談が重要です。
埋伏歯は自然には出てこないことが多いため、「歯が生えてこないな」と感じたら、早めに矯正専門医にご相談を。
Q5. 埋伏歯を放っておくとどうなりますか?
A. 他の歯を押したり、歯根を溶かしたりするリスクがあります(歯根吸収)。場合によっては歯ぐきや骨の中に嚢胞ができることも。
痛みがなくても、放置すると大きな問題に発展することがあるため注意が必要です。
Q6. 抜歯が必要なこともありますか?
A. はい。歯の向きが極端に悪い、ほかの歯に影響が大きい場合は、抜歯を選ぶこともあります。矯正専門医と口腔外科医が連携して、最も良い方法を検討します。
Q7. 費用や期間はどれくらいかかりますか?
A. 治療内容や装置の種類によって異なります。牽引治療を含む場合、通常の矯正よりも少し期間が長くなることもあります。
正確な費用や期間は、検査後のカウンセリングで詳しくご説明します。
Q8. ユアサ矯正歯科ではどんな対応をしていますか?
A. CTやレントゲンによる精密な診断を行い、必要に応じて埋伏歯の牽引や抜歯、スペース確保などの治療をご提案します。
札幌市内の提携口腔外科とも連携し、安心して治療を受けていただける体制を整えています。
Q9. 子どもの埋伏歯はどう治療するの?
A. 基本は「牽引(けんいん)治療」で自然な歯の萌出を促します。スペースを作るために矯正治療を併用することもあります。
▶ 小児期の対応の特徴
- 歯の根が完成する前に対応することで、比較的スムーズに牽引ができる
- 成長中の骨に対して、スペースを広げやすい(拡大装置など)
- 将来的な歯並びを見越したⅠ期治療(小児矯正)との連携が重要
例)
- 上あごの犬歯が生えてこない
- レントゲンで偶然見つかる
- 過剰歯による前歯の埋伏
Q10. 大人(成人)の埋伏歯はどう対応しますか?
A. 牽引が可能な場合は引き出しますが、歯の位置や周囲の状況によっては「抜歯」を選ぶこともあります。
▶ 成人の対応の特徴
- 歯根が完成し、牽引に時間がかかる・難しいケースもある
- 歯の周囲に嚢胞(のうほう)や歯根吸収などのリスクがある場合も
- 他の歯とのバランス、審美性・咬み合わせの影響を総合的に考慮
例)
- 親知らず以外の歯が横向きや逆方向に埋伏している
- 長年放置された埋伏歯が他の歯に影響を与えている
- ブリッジやインプラントを計画する前に確認が必要になることも
Q11. 子どもと大人、どちらでも埋伏歯は見つけられますか?
A. はい。レントゲンやCT検査で歯の位置や向きを確認できます。
特に、永久歯が生えてくる時期(6〜12歳頃)にレントゲンを撮ることで、早期発見・予防的対応が可能です。
Q12. 早く見つけた方がいいのはなぜ?
A. 成長期の方が治療の選択肢が広く、治療の負担も少なくて済むからです。
- 子ども:自然に生えてくるよう誘導しやすい
- 大人:骨が固くなり、牽引や移動に時間と負担がかかる
Q13. 埋伏歯の牽引治療はどんな流れですか?
- レントゲン・CTで位置を確認
- 口腔外科にて歯ぐきを開き、矯正歯科で埋伏歯に小さな装置(フックやボタン)を装着
- 矯正装置で少しずつ牽引開始
- 歯列の中に収めて、最終的な歯並びを整える
※ 成人の場合、牽引が難しい場合は抜歯や他の治療法も検討します。
◆ まとめ:年齢に応じた柔軟な対応が大切です
- 子どもは「将来を見据えた予防的な治療」
- 大人は「安全性・リスクを考慮した計画的な治療」
埋伏歯は放置するとトラブルにつながることもあるため、痛みがないからといって自己判断せず、気になる場合は一度歯科医院で相談し、適切な診断を受けることが大切です。早期に発見し、適切な処置を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、お口の健康を守ることができます。
ご自身やお子さんの歯の状態、歯並びに不安を感じている方は、一度、ユアサ矯正歯科を受診してみてください。
📞011-855-4182
📍相談予約 https://ssl.haisha-yoyaku.jp/x0836927/login/serviceAppoint/index?SITE_CODE=hp
監修者:湯浅 壽大
歯科医師・歯学博士(D.D.S., Ph.D.)
日本矯正歯科学会認定医|北海道矯正歯科学会・日本舌側矯正歯科学会 会員
2002年に北海道医療大学歯学部を卒業後、同大学大学院歯学研究科で専門性を深める。
2013年に開業して以来、矯正治療を中心に、噛み合わせや見た目の調和を重視した歯科治療を提供。
学会や勉強会に積極的に参加し、最新の矯正技術を取り入れて治療にあたっています。
詳しいプロフィールはこちらhttps://yuasa-orthodontics.com/about