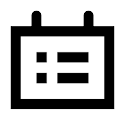反対咬合は原因の原因は大きく2つに分けることができます。 一つ目は歯が原因による場合です。 歯を原因とする反対咬合は、骨格の前後的な位置の異常はないけれど、何らかの原因で上の前歯の生える方向が悪く、内方向に生えてきてしまうことで下の前歯の裏側に入り込んでしまい、そこで咬むようになってしまうといった状態です。これは歯の生える方向や傾きを矯正装置によって調整することによって、比較的改善が容易なことが多いです。 二つ目は骨格が原因による場合です。 骨格を原因とする反対咬合は、下あごが上のあごと比べて相対的に大きかったり、前方に位置づけられている状態です。上のあごの発育がよくなくて生じる場合と下後の成長が旺盛で生じる二つのパターンが存在します。骨格が原因の場合、遺伝的要素が非常に深く関与することが多いです。たとえば患者さんの親御さんが反対咬合の場合や、たとえ親御さんが反対咬合でなかったとしても、両親のどちらの家系に反対咬合のかたがいる場合などにその症状が発現することがあります。 骨格的要素が強い場合、あごの成長発育が大きく関与しているため、矯正治療を開始する時期によって治療方針が異なります。 永久歯列であごの成長発育がほぼ終了している時期では、上あごと下あごの前後的位置や大きさの不調和が大きく、歯の位置や傾きの調整のみでは改善できないと判断される場合、抜歯や外科的矯正治療(外科的手術)を組み合わせた治療方法が検討されます。外科的矯正治療は骨格的不調和の改善を目的として行います。 乳歯列や混合歯列の段階であごの成長発育がある時期では、あごの位置や大きさを改善するための治療を行います。矯正装置で上のあごの前方への成長を促進したり、下あごの成長を抑制したりといったことになります。最近では乳歯列の時期から反対咬合を改善して正しいかみ合わせで咀嚼できるようにすることで、正しいあごの成長発育を期待するといった治療方法も存在します。そして乳歯や混合歯列の時期に反対咬合が改善されても、成長が落ち着くまでは経過を長期的に注意深く見ていく必要があります。 反対咬合は、その原因や治療を開始する時期によって治療の方法と目的が異なります。特に骨格的な不調和が原因の場合では、あごの成長発育がある時期から矯正治療を開始することで、骨格の不調和が改善され、将来的に外科的矯正治療の必要性を下げることにつながります。 ユアサ矯正歯科 湯浅壽大 https://yuasa-orthodontics.com/clinic.html
📞011-855-4182
📍相談予約 https://ssl.haisha-yoyaku.jp/x0836927/login/serviceAppoint/index?SITE_CODE=hp
監修者:湯浅 壽大
歯科医師・歯学博士(D.D.S., Ph.D.)
日本矯正歯科学会認定医|北海道矯正歯科学会・日本舌側矯正歯科学会 会員
2002年に北海道医療大学歯学部を卒業後、同大学大学院歯学研究科で専門性を深める。
2013年に開業して以来、矯正治療を専門に、噛み合わせや見た目の調和を重視した歯科治療を提供。
学会や勉強会に積極的に参加し、最新の矯正技術も取り入れて治療にあたっています。
詳しいプロフィールはこちらhttps://yuasa-orthodontics.com/about